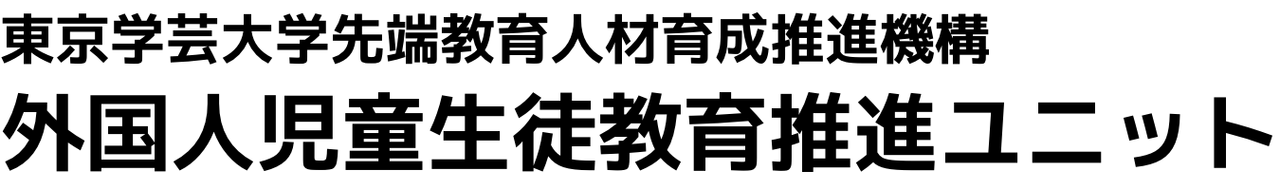2024年度実践交流会 日程・交流の概要・ねらい
実践交流会「多様性が活きることばの教育実践」(対面)
主催:東京学芸大学 先端教育人材育成推進機構・外国人児童生徒教育推進ユニット
本学外国人児童生徒教育ユニットでは、2タイプの計6回のオンライン研修に加えて、日本語教育・支援の一定の経験を有する教員・支援員・支援者の皆さんが、相互に実践を語り合い・学び合う場を設けることにしました。子どもたちも多様(言語・文化背景、来日の経緯や滞日期間、ことばの力や認知・学力の発達状態)であれば、教育・支援現場も多様(地域の多文化かの状況、組織・団体としての考え方、日本語教育・指導の仕組み、人的配置)、そして携わり者も多様(立場・教育経験・教育観・言語指導の知識・技能)です。そうした中で、様々な立場で、多くの皆さんが、子どもたちがことばを豊かに運用できる力を高めるための教育活動・支援活動に創意工夫をなさっています。この実践交流会では、そうした皆さんが、自身の実践について語り、具体的なアイディアを共有するとともに、その背後にある子ども観、学習観、言語観を交差させながら、次なる、実践を展開するための創発を得る活動をします。
1 研修実施日 (各回(青字)をクリックしてください。詳細がご覧になれます。準備できた回から公開します。 )
回
|
実施月日
申し込み期間
|
時間・会場
|
定員 |
第1回
|
8月17日(土)
|
実践交流会 時間:12:30-14:30 会場 : 東京学芸大学講義棟
|
30人 |
第2回
|
9月14日(土) |
時間 13:30-16:30
|
30人 |
第3回 |
11月9日(土) |
時間:13:30-16:30 |
30人 |
2 お申込み方法
研修日の約1か月前から、お申込みを受け付けます。定員になり次第締め切らせていただきます。
お申込みは、こくちーずpro.というサイトで手続きをお願いします。
詳細については、各研修の情報でご確認ください。
3 実践交流について
多様な言語的文化的背景を持つ子どもたちの教育・支援活動に、一定の年数携わり、経験してきた教育者(教員・支援員・支援者等)の皆さんが、日ごろの実践について相互交流することを目的としています。自身の取り組みについて、具体的な資料をもってきていただき、互いの実践について紹介し合っていただきます。ご参加なさる皆さんは、実践に関して具体的で建設的な意見交換をするためにも、取り組み・実践の様子がわかる資料をご持参ください。
取り組みとしては授業の実践のみならず、次のような場・課題場面での多様な活動を含みます。
是非、皆さんの取り組みを携えてお集まりください。
|
|
取り組みの場 |
・学校 ・組織・団体 ・行政 ・地域 ・メディア |
|
実践 |
・日本語指導・日本語学習支援 |
|
実践の様子が分かる資料の例 |
実施する際に利用したリソース(学習材や資料)、 実践の過程が分かる資料(写真・音声・記録)、実践の結果が分かる成果物(子どもたちの作品、活動の参加者のコメント関わった方々の声等) |
<ねらいとする資質・能力※>
実践交流会でも、オンライン研修同様に、多様化する学校や社会で教育を担う者の資質・能力のねらいを設定して実施します。
各回で、活動内容には多少の違いはありますが、基本的にはどの回も、次の資質・能力を育み・高めることを目指して実施します。
※文部科学省 「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」の「豆の木モデル」(日本語教育学会2019)にもとづき、下表の資質・能力の向上を目指して、各回のテーマ及び内容を設定し、目標を具体化して、研修を実施する。
|
資質・能力 |
具体的な力 |
|
|
捉える力 |
子どもの実態把握 |
ウ 子どものことばの力を、日本語と母語の両言語を視野に入れ、言語能力の多面性に留意して測定したり評価したりすることができる。 |
|
社会的背景の理解 |
オ 外国人児童生徒等教育に関する施策や制度を、自ら情報を収集して理解することができる。 |
|
|
育む力 |
日本語・教科の力の育成 |
シ 子どものニーズ、能力、学習経験に応じて個別の指導計画を作成し、日本語指導等を実施し、評価を行うことができる。 |
|
異文化間能力の涵養 |
チ 子ども の 文化間移動の経験や言語的文化的多様性を価値付け、周囲の子どもの学びに結びつける ことができる。 |
|
|
つなぐ力 |
学校づくり |
テ 外国人児童生徒等教育を学校の教育課題に位置づけ、学校全体で取り組むよう働きかけることができる。 |
|
地域づくり |
ヌ 子どもの学びが広がりと連続性をもったものになるように、地域の他校、あるいは保幼小中高の連携を進めることができる。 |
|
|
変える/変わる力 |
多文化共生社会の実現 |
ノ 外国人児童生徒等のマイノリティの立場を理解し、公正性を意識した教育・支援できる。 |
|
教師としての成長 |
ホ 実践の 質 の 向上 のために、教師集団で経験を共有したり相互に研修を行ったりすることができる。 |
|